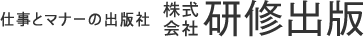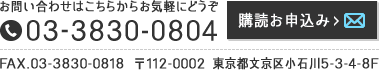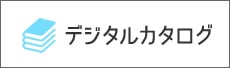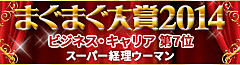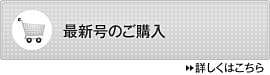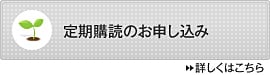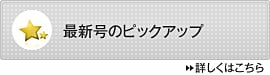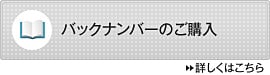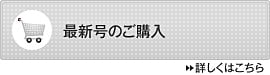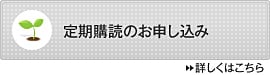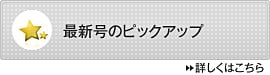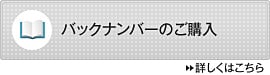月刊経理ウーマン オススメ記事のご紹介

最新号ではこんな内容が掲載されています。
■2024年11月号(10/20発行)
特別企画/
特別企画/
用紙配布が不要になり記載ミスがなくなる
… 会社にも社員にもメリットが大きい!!
… 会社にも社員にもメリットが大きい!!
年末調整の「電子化」のことが分かる3時間講座
●「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」のおさらいノート
●「労働基準監督署の調査」─こんなふうに行なわれます
●「身元保証書」にまつわる法律知識7Q7A
●「税務調査」─調査官の指摘に納得できない時の交渉術
●読書のときに使ってみたい便利グッズ大図鑑
●有名人が語る「わたしの金銭哲学」(渡辺裕太さん)
●「労働基準監督署の調査」─こんなふうに行なわれます
●「身元保証書」にまつわる法律知識7Q7A
●「税務調査」─調査官の指摘に納得できない時の交渉術
●読書のときに使ってみたい便利グッズ大図鑑
●有名人が語る「わたしの金銭哲学」(渡辺裕太さん)
今月号の記事
経理ウーマン11月号/
特別企画/用紙配布が不要になり記載ミスがなくなる
…会社にも社員にもメリットが大きい!!
…会社にも社員にもメリットが大きい!!
年末調整の「電子化」のことが分かる3時間講座
税理士 岡田和己
Lesson1 まずは年末調整の流れと「電子化」のメリットを確認しておこう
読者の皆さんは、年末調整に向けた準備で気もそぞろな時期かもしれませんね。早い会社だと従業員への用紙配布や説明が終わっている頃でしょうか。
本特集では「年末調整の電子化」について解説していきます。ひょっとしたら今年の年末調整には間に合わず、すぐに活用できないところがあるかもしれません。
読者の皆さんは、年末調整に向けた準備で気もそぞろな時期かもしれませんね。早い会社だと従業員への用紙配布や説明が終わっている頃でしょうか。
本特集では「年末調整の電子化」について解説していきます。ひょっとしたら今年の年末調整には間に合わず、すぐに活用できないところがあるかもしれません。
ですが、来年に向けて「こんなことができるんだ」「便利だな」「こんな準備が要りそうだ」などの気づきや、はたまた「今からでも活用できそうだ」と感じることもあるはずです。
ということで、まずは最初に「年末調整」の流れをつかんでおきましょう。ただ、誌面の都合で詳しく触れられない部分もありますので、もし心もとない場合は、例年本誌12月号に付いている特別付録「年末調整まるかじり」を先にお読みいただいたほうがよいかもしれません。
これまでの年末調整では、最初のステップとして、従業員に次の(1)から(5)の申告書(以下まとめて「年調書類」と呼びます)を渡して記入を依頼していました。
(1) 給与所得者の「扶養控除等(異動)」申告書
(2) 給与所得者の「基礎控除」申告書
(3) 給与所得者の「配偶者控除等」申告書
(4) 給与所得者の「所得金額調整控除」申告書
(5) 給与所得者の「保険料控除」申告書
※(2)から(4)は1枚の用紙にまとまっています。
その後、会社における年末調整業務は次ページ図表1の流れになります。
純粋な年末調整は、年税額の計算をして源泉徴収票を従業員に配布するところまでですが、本稿では給与支払報告書や法定調書まで含めて「年末調整」と呼ぶことにします。なお、図表1で「給与ソフトへ入力」と書きましたが、もしかしたらこの作業も手書きで対応されている会社があるかもしれませんね。
では、この流れを電子化するとどうなるのでしょうか? 早速確認していきましょう。
「電子化」で会社にはこんなメリットがある
皆さんは「電子化」と聞いてどんなイメージを持ちますか? 「電子化」とは、紙でやり取りしていた情報をデータに置き換えることです。つまり年末調整でいう「電子化」とは、年調用紙や控除証明書のやり取りや、従業員への源泉徴収票の交付をデータでやりましょう、ということです。
先ほど確認した(今までの)年末調整の流れを電子化したとして、従来の年末調整の流れと比較したのが次ページ図表2です。一目でパッとみて、電子化のほうが作業時間や紙の使用を減らせそうに見えませんか?
それでは、具体的なメリットを確認していきましょう。メリットは会社、従業員の双方にあるのですが、まずは会社側のメリットです。
ということで、まずは最初に「年末調整」の流れをつかんでおきましょう。ただ、誌面の都合で詳しく触れられない部分もありますので、もし心もとない場合は、例年本誌12月号に付いている特別付録「年末調整まるかじり」を先にお読みいただいたほうがよいかもしれません。
これまでの年末調整では、最初のステップとして、従業員に次の(1)から(5)の申告書(以下まとめて「年調書類」と呼びます)を渡して記入を依頼していました。
(1) 給与所得者の「扶養控除等(異動)」申告書
(2) 給与所得者の「基礎控除」申告書
(3) 給与所得者の「配偶者控除等」申告書
(4) 給与所得者の「所得金額調整控除」申告書
(5) 給与所得者の「保険料控除」申告書
※(2)から(4)は1枚の用紙にまとまっています。
その後、会社における年末調整業務は次ページ図表1の流れになります。
純粋な年末調整は、年税額の計算をして源泉徴収票を従業員に配布するところまでですが、本稿では給与支払報告書や法定調書まで含めて「年末調整」と呼ぶことにします。なお、図表1で「給与ソフトへ入力」と書きましたが、もしかしたらこの作業も手書きで対応されている会社があるかもしれませんね。
では、この流れを電子化するとどうなるのでしょうか? 早速確認していきましょう。
「電子化」で会社にはこんなメリットがある
皆さんは「電子化」と聞いてどんなイメージを持ちますか? 「電子化」とは、紙でやり取りしていた情報をデータに置き換えることです。つまり年末調整でいう「電子化」とは、年調用紙や控除証明書のやり取りや、従業員への源泉徴収票の交付をデータでやりましょう、ということです。
先ほど確認した(今までの)年末調整の流れを電子化したとして、従来の年末調整の流れと比較したのが次ページ図表2です。一目でパッとみて、電子化のほうが作業時間や紙の使用を減らせそうに見えませんか?
それでは、具体的なメリットを確認していきましょう。メリットは会社、従業員の双方にあるのですが、まずは会社側のメリットです。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン11月号/
適用条件から控除額まで 年末調整の前に知識を整理しておこう
「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」の
おさらいノート
税理士 木村聡子
「控除」には「所得控除」「税額控除」の2種類がある
筆者が税務会計業界に入る前、まだ税金シロウトだった頃の話です。ご存知のとおり医療費が多くかかった年は、確定申告で医療費控除の適用をすれば税金が戻る可能性があります。
友人「一年間で払った医療費の額から10万円を引いた額が、控除されるんだって」
私「と言うことは、去年かかった医療費は16万円だから…。ラッキー! 6万円(16万円-10万円)も税金が戻ってくるんだ!」
ところが、実際に確定申告の手引きに従い計算をしてみたら、戻ってくる額は数千円。なんともガッカリしたものです。
税計算には、計算上のルールや特典として、各種の控除があります。「控除」という言葉からくるイメージどおり、それはある金額から一定の金額を差し引くことを意味します。皆さんはこれから「〇〇控除」と名のつく税法用語に出会ったら「これは、課税所得から控除するものなのか? 税金の額から控除するものなのか?」を注意するようにしてください。
つまり「〇〇控除」には「所得控除」「税額控除」の2種類があり、「所得控除」は税額のベースになる「所得」を小さくする効果のあるものです。一方で「税額控除」は税金の額そのものを減少させます。
筆者が税務会計業界に入る前、まだ税金シロウトだった頃の話です。ご存知のとおり医療費が多くかかった年は、確定申告で医療費控除の適用をすれば税金が戻る可能性があります。
友人「一年間で払った医療費の額から10万円を引いた額が、控除されるんだって」
私「と言うことは、去年かかった医療費は16万円だから…。ラッキー! 6万円(16万円-10万円)も税金が戻ってくるんだ!」
ところが、実際に確定申告の手引きに従い計算をしてみたら、戻ってくる額は数千円。なんともガッカリしたものです。
税計算には、計算上のルールや特典として、各種の控除があります。「控除」という言葉からくるイメージどおり、それはある金額から一定の金額を差し引くことを意味します。皆さんはこれから「〇〇控除」と名のつく税法用語に出会ったら「これは、課税所得から控除するものなのか? 税金の額から控除するものなのか?」を注意するようにしてください。
つまり「〇〇控除」には「所得控除」「税額控除」の2種類があり、「所得控除」は税額のベースになる「所得」を小さくする効果のあるものです。一方で「税額控除」は税金の額そのものを減少させます。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン11月号/
修正申告に応じる? 更正決定処分を待つ?
「税務調査」─調査官の指摘に納得できない時の交渉術
税理士 渡邊勝也
はじめまして。税理士法人クオリティ・ワン(以下、クオリティ・ワン)の渡邊勝也と申します。弊社は創業以来14年間、税務調査専門税理士法人として活動してきており、現在、年間・約130件以上の税務調査対応を行なっています。弊社の対応スタンスは次の3つです。
・合法的に納税額を減らす(平均減少率50%)
・早く税務調査を終わらす(平均調査時間2時間)
・調査官とはWIN-WINの関係を築く(精神的負担が少ない)
本稿では税務調査の交渉術について、「担当官は何をしてくるのか?」「どう交渉すると納得してくれるか?」などを解説していきます。それによって少しでも税務調査に対する不安が少なっていただければと思います。
まずは税務調査の基本を押さえておこう
税務調査での交渉術の前に、まず税務調査とはどういうものなのか? また税務調査ではどういうことが行なわれるのか?を知っておくことが必要です。
「税務調査は何をやってくるかわからない」とよく言われていますが、相手のことを知ることで、その対策・事前準備に万全を期すことができ、担当官といざ交渉となったとしてもより上手く対応できるようになるからです。
まず税務調査とはどういうものなのか?についてです。ひと口に税務調査といっても大きく分けると2種類あります。1つは強制調査、そしてもう1つは任意調査です。1つ目の強制調査は、国税局にある査察部門(通称「マルサ」)による調査です。
そしてもう1つの任意調査が、皆さんがよく耳にする税務調査となります。こちらは大きく分けて次の2種類があります。
・合法的に納税額を減らす(平均減少率50%)
・早く税務調査を終わらす(平均調査時間2時間)
・調査官とはWIN-WINの関係を築く(精神的負担が少ない)
本稿では税務調査の交渉術について、「担当官は何をしてくるのか?」「どう交渉すると納得してくれるか?」などを解説していきます。それによって少しでも税務調査に対する不安が少なっていただければと思います。
まずは税務調査の基本を押さえておこう
税務調査での交渉術の前に、まず税務調査とはどういうものなのか? また税務調査ではどういうことが行なわれるのか?を知っておくことが必要です。
「税務調査は何をやってくるかわからない」とよく言われていますが、相手のことを知ることで、その対策・事前準備に万全を期すことができ、担当官といざ交渉となったとしてもより上手く対応できるようになるからです。
まず税務調査とはどういうものなのか?についてです。ひと口に税務調査といっても大きく分けると2種類あります。1つは強制調査、そしてもう1つは任意調査です。1つ目の強制調査は、国税局にある査察部門(通称「マルサ」)による調査です。
そしてもう1つの任意調査が、皆さんがよく耳にする税務調査となります。こちらは大きく分けて次の2種類があります。
(詳しくは本誌をご覧ください)
前月号の記事
経理ウーマン10月号/
特集企画/来年4月から65歳までの雇用確保が義務化される!!
人件費の増加 組織の高齢化にどう対応する?
人件費の増加 組織の高齢化にどう対応する?
「定年延長」─中小企業の緊急対策マニュアル
特定社会保険労務士 本田和盛
LESSON1 来年4月からの「65歳までの雇用確保の義務化」とはこんな内容です
多くの会社では定年など従業員の雇用上限年齢を定めています。この雇用上限年齢に関して来年4月に大きな改正が行なわれます。具体的には、2025年3月に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」の経過措置が終了し、「65歳までの雇用確保措置」(以下、高年齢者雇用確保措置)が4月から完全義務化されます。
読者の中には、いよいよこれで我が国も「65歳定年制」が法的義務になるのかと思われた方もいると思います。また「65歳までの雇用確保はこれまでも義務だったのではないの?」「当社では社員は65歳まで普通に働いているので、65歳ではなく70歳までの雇用確保の間違いでは?」と首を傾げた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、これまでも高年齢者雇用確保措置は法的義務でした。つまり希望者全員を65歳まで雇用することが建前上は義務となっていました。しかしその法的義務には抜け穴があって、一部の社員を雇用確保措置の対象から除外することができていたのです。しかし来年4月からはこの抜け穴(経過措置という)が実質的に無くなり、希望者全員を対象にした制度へと完全移行(完全義務化)することとなります。
また多くの方が誤解していますが、高年齢者雇用確保措置の完全義務化と「65歳定年制」はイコールではありません。定年は今までどおり60歳のままでもなんら問題はありません。何らかの形で希望する全社員を65歳まで雇用すればよいだけです。
LESSON1では、来年4月の高年齢者雇用確保措置の完全義務化を前に、これまでの高年齢者を対象とした雇用制度の流れを振り返りながら、今回の高年齢者雇用確保措置の義務化の背景や、現下の高年齢者雇用の状況、高年齢者雇用の今後について見ていくことにしましょう。
完全義務化は40年前からの構想!?
最初に、高齢者と高年齢者の違いについて説明しておきます。普段私たちはこの2つの言葉を同じような意味で使っていますが、実はまったく異なります。
「高齢者」は主に医療など社会保障の領域で使われる言葉で、65歳以上の方を指す言葉です。65歳以上の高齢者のうち65~74歳を前期高齢者、75歳以上は後期高齢者と呼ばれます。健康保険制度など一般の医療保険制度に入っている雇用者も、75歳になればそこから抜けて後期高齢者医療制度に入り直すことになります。
多くの会社では定年など従業員の雇用上限年齢を定めています。この雇用上限年齢に関して来年4月に大きな改正が行なわれます。具体的には、2025年3月に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」の経過措置が終了し、「65歳までの雇用確保措置」(以下、高年齢者雇用確保措置)が4月から完全義務化されます。
読者の中には、いよいよこれで我が国も「65歳定年制」が法的義務になるのかと思われた方もいると思います。また「65歳までの雇用確保はこれまでも義務だったのではないの?」「当社では社員は65歳まで普通に働いているので、65歳ではなく70歳までの雇用確保の間違いでは?」と首を傾げた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、これまでも高年齢者雇用確保措置は法的義務でした。つまり希望者全員を65歳まで雇用することが建前上は義務となっていました。しかしその法的義務には抜け穴があって、一部の社員を雇用確保措置の対象から除外することができていたのです。しかし来年4月からはこの抜け穴(経過措置という)が実質的に無くなり、希望者全員を対象にした制度へと完全移行(完全義務化)することとなります。
また多くの方が誤解していますが、高年齢者雇用確保措置の完全義務化と「65歳定年制」はイコールではありません。定年は今までどおり60歳のままでもなんら問題はありません。何らかの形で希望する全社員を65歳まで雇用すればよいだけです。
LESSON1では、来年4月の高年齢者雇用確保措置の完全義務化を前に、これまでの高年齢者を対象とした雇用制度の流れを振り返りながら、今回の高年齢者雇用確保措置の義務化の背景や、現下の高年齢者雇用の状況、高年齢者雇用の今後について見ていくことにしましょう。
完全義務化は40年前からの構想!?
最初に、高齢者と高年齢者の違いについて説明しておきます。普段私たちはこの2つの言葉を同じような意味で使っていますが、実はまったく異なります。
「高齢者」は主に医療など社会保障の領域で使われる言葉で、65歳以上の方を指す言葉です。65歳以上の高齢者のうち65~74歳を前期高齢者、75歳以上は後期高齢者と呼ばれます。健康保険制度など一般の医療保険制度に入っている雇用者も、75歳になればそこから抜けて後期高齢者医療制度に入り直すことになります。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン10月号/
耐用年数の計算方法から節税になるカラクリまで
「中古資産」の減価償却の仕方が分かる講座
税理士 鈴木まゆ子
建物や車、パソコンやコピー機など、法人が事業で使う固定資産を中古で買うことがあります。ここで注意したいのが減価償却です。
中古の場合は新品とは減価償却の考え方が異なります。知らないと税金で損をすることもあり得ます。逆に知っておくことで節税につながる場合もあります。本稿では、法人の中古資産の減価償却の特徴、カギとなる「耐用年数」の中身、注意点を解説します。
中古資産の減価償却で注意したいのは「耐用年数」
まずは法人税の減価償却限度額の計算式を復習しつつ、中古資産の耐用年数の考え方を確認しましょう。
中古の固定資産でも、税法上の減価償却限度額の計算は新品と同じです。主な減価償却の方法は「定額法」「定率法」ですが、平成19年4月1日以降の取得分の計算式は、それぞれ次ページ図表1のようになっています。期中に取得した場合は、月数按分が必要です。また、取得価額は資産の購入額だけでなく、据付費用などの付随費用も加えたものとなります。
ただし、中古資産の減価償却計算は新品のそれと同じでも、用いる償却率は新品と同じとは限りません。なぜなら、償却率を決める要素である耐用年数は、中古資産の取得時の状況によって変わるからです(次ページ図表2)。
新品の固定資産は「一度も使われたことがなく、劣化していない」という共通点があります。そのため、資産の種類と細目(資産の使用目的)が分かれば、一律で使用可能期間を表す耐用年数が決まります。
実際、会計ソフトではこの2つさえ入力すれば自動的に法定耐用年数が決まり、償却率が表示されます。資産の取得時の状況を個別に考える必要はありません。
中古の場合は新品とは減価償却の考え方が異なります。知らないと税金で損をすることもあり得ます。逆に知っておくことで節税につながる場合もあります。本稿では、法人の中古資産の減価償却の特徴、カギとなる「耐用年数」の中身、注意点を解説します。
中古資産の減価償却で注意したいのは「耐用年数」
まずは法人税の減価償却限度額の計算式を復習しつつ、中古資産の耐用年数の考え方を確認しましょう。
中古の固定資産でも、税法上の減価償却限度額の計算は新品と同じです。主な減価償却の方法は「定額法」「定率法」ですが、平成19年4月1日以降の取得分の計算式は、それぞれ次ページ図表1のようになっています。期中に取得した場合は、月数按分が必要です。また、取得価額は資産の購入額だけでなく、据付費用などの付随費用も加えたものとなります。
ただし、中古資産の減価償却計算は新品のそれと同じでも、用いる償却率は新品と同じとは限りません。なぜなら、償却率を決める要素である耐用年数は、中古資産の取得時の状況によって変わるからです(次ページ図表2)。
新品の固定資産は「一度も使われたことがなく、劣化していない」という共通点があります。そのため、資産の種類と細目(資産の使用目的)が分かれば、一律で使用可能期間を表す耐用年数が決まります。
実際、会計ソフトではこの2つさえ入力すれば自動的に法定耐用年数が決まり、償却率が表示されます。資産の取得時の状況を個別に考える必要はありません。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン10月号/
将来を見据えて今身に付けるべき資質はこれだ!!
AI時代に生き残るための「経理スキル」の磨き方
ユナイテッド・パートナーズ会計事務所
パートナー・税理士 森田貴子
パートナー・税理士 森田貴子
AIの進化で"先生"と呼ばれる職業は稼げなくなる。私たち税理士の業界にもそのような声が聞こえてきます。テクノロジーの進化により、AI(人工知能)やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)がバックオフィスでの仕事を大きく変えつつあります。この変化はどのように進んでいくのでしょうか?
はじめまして、森田貴子と申します。税理士として29年、会計事務所を立ち上げて21年目になります。「月刊経理WОMAN」でみなさんにメッセージさせていただくのは15年ぶりとなります。2007年には「税務手続きの電子化」、2008年には「経理のプロ養成講座」について書かせていただきました。当時と現在を振り返っても、経理の重要性に対する私の考えは変わりません。
経理はどの会社にも必ず存在します。欠かせない存在で、会社が変わってもスキルが積み上がる仕事です。女性のライフスタイルの変化にも対応しやすく、経営をサポートすることを通じて社会に貢献できる誇り高い職業です。決して華やかさはないかもしれませんが、コツコツと続けられる素晴らしい仕事です。
しかし、スコアキーパーとしての役割は減少していく可能性があります。そのため、環境の変化に対応し、意思決定に必要な情報を作成する時間を確保する工夫や継続する学びが重要です。本稿の最後には、その具体的な方法についてもお伝えさせていただきますね。
さて、ずっと現場にいた私からバックオフィスの未来予測です。私は経理の仕事がなくなることはないと考えています。ただし、新しいテクノロジーの進化により、ちょっとした工夫が必要になることは避けられません。そして不変的に大切なこともあります。
皆さんには「不安にならなくて大丈夫!」というメッセージをお届けしたいです。経理担当者に求められるスキルやスキルを磨くための方法について、本稿でお話しさせていただきます。変化に対応しながら、安心して未来を迎えましょう。
経理を取り巻く環境は大きく変化している
30年以上前、私が税理士試験を目指していた頃、「経理や税理士の仕事は電子化が進むので、資格を取っても意味がないかもしれないよ」とアドバイスを受け、不安になったことがあります。それでも簿記の勉強を続け、資格を取得し、実務を積んできた結果、学び続けて良かったと感じています。
はじめまして、森田貴子と申します。税理士として29年、会計事務所を立ち上げて21年目になります。「月刊経理WОMAN」でみなさんにメッセージさせていただくのは15年ぶりとなります。2007年には「税務手続きの電子化」、2008年には「経理のプロ養成講座」について書かせていただきました。当時と現在を振り返っても、経理の重要性に対する私の考えは変わりません。
経理はどの会社にも必ず存在します。欠かせない存在で、会社が変わってもスキルが積み上がる仕事です。女性のライフスタイルの変化にも対応しやすく、経営をサポートすることを通じて社会に貢献できる誇り高い職業です。決して華やかさはないかもしれませんが、コツコツと続けられる素晴らしい仕事です。
しかし、スコアキーパーとしての役割は減少していく可能性があります。そのため、環境の変化に対応し、意思決定に必要な情報を作成する時間を確保する工夫や継続する学びが重要です。本稿の最後には、その具体的な方法についてもお伝えさせていただきますね。
さて、ずっと現場にいた私からバックオフィスの未来予測です。私は経理の仕事がなくなることはないと考えています。ただし、新しいテクノロジーの進化により、ちょっとした工夫が必要になることは避けられません。そして不変的に大切なこともあります。
皆さんには「不安にならなくて大丈夫!」というメッセージをお届けしたいです。経理担当者に求められるスキルやスキルを磨くための方法について、本稿でお話しさせていただきます。変化に対応しながら、安心して未来を迎えましょう。
経理を取り巻く環境は大きく変化している
30年以上前、私が税理士試験を目指していた頃、「経理や税理士の仕事は電子化が進むので、資格を取っても意味がないかもしれないよ」とアドバイスを受け、不安になったことがあります。それでも簿記の勉強を続け、資格を取得し、実務を積んできた結果、学び続けて良かったと感じています。
(詳しくは本誌をご覧ください)
前々月号の記事
経理ウーマン9月号/
特別企画/直近の経営課題を把握して早急に手を打つ!
社長と経理が知っておきたい!!
社長と経理が知っておきたい!!
「月次決算書」の正しい読み方&活かし方
税理士法人古田土会計取締役/税理士 川名 徹
月次決算の4つのメリットとは
中小企業にとって月次決算は経営の羅針盤とも言える重要なツールです。月次決算書を毎月作成し、分析することで、経営者は会社の現状を正確に把握し、適切な意思決定を行なうことができます。
古田土会計グループでは約4000社の顧問先があり、年商5000万円~50億円の規模の中小企業の月次決算のお手伝いをしています。月次決算書を使いながら毎月数字の説明をすることで、多くの経営者、経理の方が数字に強くなり、数字で経営判断ができるようになっています。
本稿では月次決算書をどう作り、どのように活用すれば良いのかを解説していきますが、その前に「月次決算がなぜ大切なのか」についてお話ししておきましょう。
世の中には月次決算書を作らず、本決算の時にだけ数字をまとめ、慌てて税務申告をしている会社も多くあります。義務として年に1回の決算書だけ作れば誰からも文句を言われることはありませんが、それでは自社の現状を適切に把握することが難しく、感覚に頼った経営になってしまいます。月次決算を行なうことで、以下の効果を得ることができます。
1. 早い経営判断ができる
月次決算を行なうことで、期の途中でもリアルタイムに業績を捉えることができます。感覚ではなく数字で把握することによって、当月から素早く対策が打てるようになります。
本決算による決算書は、通常、決算月から約2ヵ月後に出来上がります。ですから、年に1回、ようやく決算書ができあがってから1年分の数字を確認・分析しているようでは経営という観点ではもはや手遅れです。半年や四半期に1回、数字をまとめている会社もあると思いますが、市場の変化に迅速に対応するために、中小企業であっても最低1ヵ月に1回、数字をまとめる月次決算に取り組むべきです。
古田土会計グループでは約4000社の顧問先があり、年商5000万円~50億円の規模の中小企業の月次決算のお手伝いをしています。月次決算書を使いながら毎月数字の説明をすることで、多くの経営者、経理の方が数字に強くなり、数字で経営判断ができるようになっています。
本稿では月次決算書をどう作り、どのように活用すれば良いのかを解説していきますが、その前に「月次決算がなぜ大切なのか」についてお話ししておきましょう。
世の中には月次決算書を作らず、本決算の時にだけ数字をまとめ、慌てて税務申告をしている会社も多くあります。義務として年に1回の決算書だけ作れば誰からも文句を言われることはありませんが、それでは自社の現状を適切に把握することが難しく、感覚に頼った経営になってしまいます。月次決算を行なうことで、以下の効果を得ることができます。
1. 早い経営判断ができる
月次決算を行なうことで、期の途中でもリアルタイムに業績を捉えることができます。感覚ではなく数字で把握することによって、当月から素早く対策が打てるようになります。
本決算による決算書は、通常、決算月から約2ヵ月後に出来上がります。ですから、年に1回、ようやく決算書ができあがってから1年分の数字を確認・分析しているようでは経営という観点ではもはや手遅れです。半年や四半期に1回、数字をまとめている会社もあると思いますが、市場の変化に迅速に対応するために、中小企業であっても最低1ヵ月に1回、数字をまとめる月次決算に取り組むべきです。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン9月号/
取得価額はどう計算する? 含み益・含み損の扱いはどうなる?
会社が保有する「上場株式」の評価方法と税務取扱い
公認会計士・税理士 大西康記
まずは有価証券の税務上の区分を知っておく
会社が保有する上場株式は有価証券ですが、まずは有価証券にはどのようなものがあるか、そして税務上どのように区分されているかについて確認しておきましょう。代表的な有価証券としては、株式(上場、非上場含む)、国債・地方債・社債等の債券があります。また他にも投資信託や新株予約権なども有価証券の範囲に入ります。
これら有価証券の税務上の区分は次ページ図表1のとおりです。
図表にもあるように、有価証券はまず「売買目的有価証券」と「売買目的外有価証券」に分類されます。「売買目的有価証券」は、会社の中のトレーディング業務を行なう専門部署が短期売買目的で取得・売買する有価証券のことです。一般の事業会社では、売買目的有価証券を扱うのは稀だと思います。
「売買目的外有価証券」は、「満期保有目的等有価証券」と「その他有価証券」に分類されます。「満期保有目的等有価証券」は償還期限の定めのある債券で満期まで保有する目的のものや子会社株式などが該当します。そして、それ以外の有価証券は「その他有価証券」に区分されます。
そしてここでもう一つ、貸借対照表の表示の話をしておきます。図表2をご覧ください。「売買目的有価証券」は短期売買となりますので、貸借対照表の「流動資産の部」に「有価証券」という科目で表示されます。
また「満期保有目的等有価証券」は、決算期末時点で償還期限が1年内にくる債券が「有価証券」、1年超の債券が「投資有価証券」、子会社株式は「関係会社株式」の科目で表示します。そして最後に「その他有価証券」は、固定資産の部に「投資有価証券」の科目で表示します。(詳しくは本誌をご覧ください)
会社が保有する上場株式は有価証券ですが、まずは有価証券にはどのようなものがあるか、そして税務上どのように区分されているかについて確認しておきましょう。代表的な有価証券としては、株式(上場、非上場含む)、国債・地方債・社債等の債券があります。また他にも投資信託や新株予約権なども有価証券の範囲に入ります。
これら有価証券の税務上の区分は次ページ図表1のとおりです。
図表にもあるように、有価証券はまず「売買目的有価証券」と「売買目的外有価証券」に分類されます。「売買目的有価証券」は、会社の中のトレーディング業務を行なう専門部署が短期売買目的で取得・売買する有価証券のことです。一般の事業会社では、売買目的有価証券を扱うのは稀だと思います。
「売買目的外有価証券」は、「満期保有目的等有価証券」と「その他有価証券」に分類されます。「満期保有目的等有価証券」は償還期限の定めのある債券で満期まで保有する目的のものや子会社株式などが該当します。そして、それ以外の有価証券は「その他有価証券」に区分されます。
そしてここでもう一つ、貸借対照表の表示の話をしておきます。図表2をご覧ください。「売買目的有価証券」は短期売買となりますので、貸借対照表の「流動資産の部」に「有価証券」という科目で表示されます。
また「満期保有目的等有価証券」は、決算期末時点で償還期限が1年内にくる債券が「有価証券」、1年超の債券が「投資有価証券」、子会社株式は「関係会社株式」の科目で表示します。そして最後に「その他有価証券」は、固定資産の部に「投資有価証券」の科目で表示します。(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン9月号/
社員旅行 懇親会 リゾート会員権…
給与課税されないためにはこうする
給与課税されないためにはこうする
会社負担のレクリエーション費用の
「税務取扱い」が分かるセミナー
税理士 鈴木裕子
ITの発展やリモートワークの定着などにより、社内で従業員同士が顔を合わせる機会が減り、コミュニケーション不足が生じていると感じることはありませんか? あるいは社内で顔は合わせていても、コロナ禍をきっかけに飲み会など社外で話す機会が減り、上司、部下や同僚とゆっくり話すことがなかなかないということもあるかもしれません。
そうした場合、従業員同士のコミュニケーションの活性化のために、社内レクリエーションが効果的です。
福利厚生の充実は、従業員の満足度向上と企業の成長に大きく貢献します。社内レクリエーションの実施により、コミュニケーションが円滑になれば、業務効率が上がり、仕事が円滑に進むなど、仕事の生産性を上げることにつながります。
また、社内レクリエーションの実施には、従業員のリフレッシュ、従業員一人ひとりのモチベーションの向上、社内の一体感の強化など、さまざまな効果が期待されます。国内や海外の慰安旅行を実施し、従業員同士で寝食を共にすると、仲良くなったり、親睦を深めたりして、業務効率アップが見込めるかもしれません。
このように社内レクリエーションにはメリットがたくさんありますが、経理担当者の立場からすると、社内レクリエーションの費用を会社が負担した場合、全額経費として認められるのかな?と気になりますよね。以下に詳しく社内レクリエーションの税務の取扱いをみていきましょう。
社内旅行の税務取扱いはこうなっています
社内レクリエーションとして慰安旅行を実施する場合、その費用の税務取扱いはどうなるのでしょう。旅行の費用を福利厚生費として経費に落とすには、注意が必要です。会社が負担した費用が、参加した従業員の給与等として課税されてしまう場合があるためです。
じつは、慰安旅行の会社負担分は、原則として給与等に該当するとされているのです。会社が従業員に与える経済的利益という扱いになるからですね。ただし、一定の要件を満たせば、参加した従業員の給与等としなくてもよいことになっており、その場合は、会社負担額を福利厚生費として経費にすることができます。
福利厚生の充実は、従業員の満足度向上と企業の成長に大きく貢献します。社内レクリエーションの実施により、コミュニケーションが円滑になれば、業務効率が上がり、仕事が円滑に進むなど、仕事の生産性を上げることにつながります。
また、社内レクリエーションの実施には、従業員のリフレッシュ、従業員一人ひとりのモチベーションの向上、社内の一体感の強化など、さまざまな効果が期待されます。国内や海外の慰安旅行を実施し、従業員同士で寝食を共にすると、仲良くなったり、親睦を深めたりして、業務効率アップが見込めるかもしれません。
このように社内レクリエーションにはメリットがたくさんありますが、経理担当者の立場からすると、社内レクリエーションの費用を会社が負担した場合、全額経費として認められるのかな?と気になりますよね。以下に詳しく社内レクリエーションの税務の取扱いをみていきましょう。
社内旅行の税務取扱いはこうなっています
社内レクリエーションとして慰安旅行を実施する場合、その費用の税務取扱いはどうなるのでしょう。旅行の費用を福利厚生費として経費に落とすには、注意が必要です。会社が負担した費用が、参加した従業員の給与等として課税されてしまう場合があるためです。
じつは、慰安旅行の会社負担分は、原則として給与等に該当するとされているのです。会社が従業員に与える経済的利益という扱いになるからですね。ただし、一定の要件を満たせば、参加した従業員の給与等としなくてもよいことになっており、その場合は、会社負担額を福利厚生費として経費にすることができます。
(詳しくは本誌をご覧ください)
「月刊経理ウーマン」
●創刊:1996年4月●体裁:A5判、縦組、116ページ ●発行日:毎月20日●年間購読料:10,865円(税・送料込)
●創刊:1996年4月●体裁:A5判、縦組、116ページ ●発行日:毎月20日●年間購読料:10,865円(税・送料込)